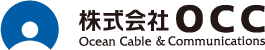沿革
日本の通信の歴史とともに歩んできたOCC
1870年(明治3年)デンマーク国王の使節が来日の上、政府に対し、自国の大北電信会社(The Great Northern Telegraph Co.)に長崎・神戸・大阪・横浜などの主要海岸都市への海底ケーブル陸揚権を与えるように交渉、翌4年に長崎・上海間と長崎・ウラジオストック間にそれぞれ1心の電信ケーブルを敷設。そして海底ケーブルの役割は、外交上・産業上・軍事上等においてますます重要なものとして展開していくものと思われます。
その前身となっているのは、日本海底電線株式会社と大洋海底電線株式会社の2つの会社です。1964年(昭和39年)2社が合併し日本大洋海底電線株式会社が発足いたしました。そして、1999年(平成11年)に商号を「株式会社OCC」と改め、今日に至っています。
創業とその後の発展
かねて逓信省は海底ケーブルの需要が限定的であることから、古河電気工業・住友電線(現・住友電気工業)・藤倉電線(現・フジクラ)の3社が共同して製造工場を持つことが経済合理性に適うと考えていました。この逓信省の考え方に基づいて、大阪の住友電線所有の海底ケーブル専門工場(大阪市大正区鶴浜通-現在の鶴町)と、横浜の古河電気工業所有の海底ケーブル工場(横浜市神奈川区平沼町)を合わせ、これに藤倉電線の経営参加を得て、3社で新会社を設立することに合意し、1935年(昭和10年)6月、資本金200万円で日本海底電線株式会社(本社-大阪市大正区)として業務を開始しました。以降、年ごとに逓信省や陸海軍、それに朝鮮・台湾の総督府などから電信・電話用ケーブルの注文が相次ぎました。その後日本の海外活動活発化による需要増大に伴い、大阪工場は大幅に拡張されました。また、横浜工場は立地場所の不便さから新しい土地が検討され、敷設船の接岸可能な横浜市神奈川区出田町に土地を求め、外装専門の新工場を建設することになり、1939年(昭和14年)12月着工、1941年(昭和16年)6月に完成しました。
本社の東京移転と戦災・復興
1944年(昭和19年)4月には軍需工場の指定を受ける等の情勢変化に伴い、同年6月、大阪市大正区の本社を東京・銀座に移し、さらに1945年(昭和20年)4月には東京都芝区神谷町に移しました。
大阪工場は1945年(昭和20年)3月と6月に2度の空襲を受け、ほとんどを焼失しました。横浜工場は同年5月以降度々の空襲を受けましたが、幸い被害は軽微でした。また、神谷町の本社も戦災を免れました。
1945年(昭和20年)8月の終戦に伴い、復興に向けて動き出しましたが、従業員の離散、役員の公職追放、国土縮小による通信用海底ケーブル需要の激減、物資の不足等の問題の中、復興には時間を要しましたが、日本経済の復興により順次元通りの活況を呈するに至りました。
PE海底ケーブルの製造開始
従来海底ケーブルの絶縁物には ガッタパーチャ(GP)という天然の熱帯樹の樹液から採取されたものが用いられていましたが、光・熱・酸素に対して弱く、劣化しやすいほか、絶縁体としては電気的性能もそれほど良いものではなく、特に高周波特性は劣っていることが認められていました。
それに対し、戦前英国で発明されたポリエチレン(PE)は1943年(昭和18年)には米国で量産され軍需用途に使われ始め、極めて安定かつ良好な特性を持つことが知られていましたが、国内で一般に出回るようになったのは戦後数年経ってからです。1950年(昭和25年)3月、横浜工場でいち早くこれに目をつけ国内他社に先駆けて試作に取り掛かりました。
これと前後して電気通信省(逓信省より改称)で北海道・噴火湾(別名・内浦湾)の室蘭〜砂原間に搬送海底ケーブルの計画が持ち上がり、当時既に良質のGPが入手し難くなっていたことから、PE絶縁ケーブルの採用を巡って古河電気工業・住友電気工業・藤倉電線と日本海底電線のメーカー4社を入れた検討会が持たれました。1951年(昭和26年)2月に4社分割発注が決定され、当社は全長40kmの内、半分近い17kmの絶縁製造を分担することが決定しました。接続方法その他、克服すべき問題点が多々ありましたが、同年10月無事敷設を完了し、新技術で大いに貢献することができました。以降、PEの優秀さから、海底ケーブルの絶縁材料は順次GPからPEへと代わっていきました。
陸上用ケーブルの製造開始
上記のPEは陸上ケーブルでも有用であることから、PEを絶縁に用いたものとして、村落部分の電話配線用ケーブルに用いるRDワイヤー(Rural Distribution Wire)の開発に成功し、1955年(昭和30年)電電公社(逓信省から電気通信省に、また1952年(昭和27年)からは電電公社に替わった-以降「NTT」と略す)の認定品となり大量受注をし、大阪工場で製造が行われました。RDワイヤー以外にも都会の家庭への配線に必要なドロップワイヤー、RDワイヤーの改良型であるSDワイヤー、さらにはテレビ共聴用同軸ケーブルやテレビカメラケーブル等、テレビの普及以前にいち早く開発を済ませ、日本のプラスチック絶縁ケーブルの先駆けとして大きな足跡を残しました。
上三川工場の操業開始
1961年(昭和36年)栃木県上三川町からの誘致により土地を購入し、1963年(昭和38年)工場の操業を開始しました(1964年(昭和39年)から独立した工場組織となりました)。後にNTTに納入する局内ケーブルやCCPケーブル等の陸上ケーブルの生産拠点となりました。
創業と第1太平洋ケーブルの製造
1956年(昭和31年)英国と米国・カナダを結ぶ第1大西洋横断電話ケーブルが完成、翌年の米国本土とハワイを結ぶケーブルの完成に伴い、日米間のケーブルが具体化し、1959年(昭和34年)5月、郵政省から日米横断電話ケーブルの実施計画が発表され、古河電気工業・住友電気工業・藤倉電線の3社が関心を示し、委員会を結成して準備に入りました。政府や関係方面の調整を終えて、1960年(昭和35年)6月に資本金4億円(後に12億円に増資)の大洋海底電線株式会社が発足しました。
工場用地は紆余曲折が有りましたが、横浜市中区新山下町と決まり、米国Western Electric社の技術援助のもと、3社の協力で建設が進められ、1963年(昭和38年)1月に竣工、3社からの派遣者を含め要員の訓練を終えて、同年4月から翌年2月の間、第1太平洋ケーブル(TPC-1)として日本・グアム間のSDケーブル2,700kmを製造し、5月初旬に敷設が完了しました。このケーブル製造に引き続きグアム・フィリピン間640kmも製造納入されました。
合併
最新鋭の設備を持つものの、太平洋横断ケーブルの仕事が一段落すると空白期間が生ぜざるを得ない大洋海底電線、海底電線のみならず陸上用電線の製造販売にも進出して堅実な経営をもって業界に独自の地位を占める日本海底電線。その両社が合併することにより、規模の拡大と全般的合理化、国際競争力を高めることが望ましいとの考えで、両社の株主である3社(古河電気工業・住友電気工業・藤倉電線)と両社の首脳陣の意見が一致し、1964年(昭和39年)10月1日に資本金16億2千万円の日本大洋海底電線株式会社が発足しました。
上三川工場の建設と陸上用ケーブルの進展
NTT向けのプリント局内ケーブルの需要を満たすため、合併後、間もなく建設が本格化しました。1964年(昭和39年)12月に3,000m²の建屋が完成し、翌年1月から本格製造を開始しました。その後1965年(昭和40年)と1967年(昭和42年)、さらには1970年(昭和45年)にはCCP ケーブルの生産を目指して、次々拡張工事が行われ、陸上用通信ケーブルの生産拠点として生産量は飛躍的に拡大し、現在の上三川事業所となりました。
長距離海底同軸ケーブルシステムの進展
第1太平洋ケーブルに引き続き、NTT向け備讃海峡用4チューブ海底同軸ケーブルを製造し、1965年(昭和40年)9月に製造納入しました。1968年(昭和43年)9月には直江津・ナホトカ間の日本海ケーブルを、1969年(昭和44年)9月にはNTTと共同で開発した国産初の900回線有中継海底同軸ケーブルを北海道の噴火湾に夫々製造納入しました。
この後納入した主なプロジェクトは次の通りです。西独・スウェーデン間(1973年)、第2太平洋(TPC-2)、SFケーブル(日本・ハワイ間 2,360km(1973〜1974年))、日中ケーブル(1975年)、沖縄・フィリピン間(1976年)、デンマーク・ノルウエー間(1976年)、東西マレーシア間およびインドネシア・シンガポール間(1978年)、タイ・マレーシア・シンガポール間(1981年)、ノーフォーク・オークランド間(ANZCANの一部)(1981年)、デンマーク・オランダNo.4(1981年)、メダン・コロンボケーブル(SEA-ME-WEの一部)(1982年)等であり、納入地域は遠く欧州にまで及んでいます。
海底光ケーブルの開発と発展
1970年代半ばから、光ファイバの低損失と広帯域性に着目して、NTT、KDDの他、海外の主要研究機関で海底光ケーブル方式の研究が開始され、当社でも順次研究陣容の強化を図り、1983年(昭和58年)にはNTTとKDDの研究所に対して、商用試験用のケーブルを出荷し、本邦初の1.3μm帯SMファイバ実用システムとして1984年(昭和59年)にNTTの本土縦貫光ケーブル幹線の一環である、津軽海峡および噴火湾のケーブルを納入し、敷設されました。
一方、第3太平洋横断ケーブル(TPC-3)を目指してKDDを中心に実験が繰り返され、1.3μm帯SMファイバを用いたOS-280方式(再生中継方式)用として、1986年(昭和61年)からケーブルの製造開始、1988年(昭和63年)に日本・グアム・ハワイ間のケーブルを製造納入しました。このシステムでは海中分岐装置が組み込まれ、以降大洋の真ん中でケーブル分岐される方式が一般的となりました。
この後海底光ケーブルシステムは技術進歩が著しく、さらに低損失な1.55μm帯SMファイバを用いたOS-560方式(再生中継方式)の第4太平洋横断ケーブル(TPC-4)を1992年(平成4年)に製造納入しました。また、再生中継方式はさらに効率的な光直接増幅方式に代り、OS-A方式の第5太平洋横断ケーブル(TPC-5)を1995年(平成7年)に製造納入しました。この海底光ケーブルシステムの進展は著しく、「海底光ケーブル海外敷設図」に見られるように、数多くのシステムを製造納入しています。
一方、国内の離島間に主として用いられる無中継の光ファイバシステムは順次多心化が進み、1993年(平成5年)には 100心海底光ケーブルがNTTと共同で開発・実用化されました。
海洋開発等特殊ケーブルの生産
海底ケーブルシステムの製造で培った技術はケーブルのみならず、周辺機器や接続技術、さらには現地施工にまでおよび、1973年(昭和48年)には地中2,000mの深層地震計システムを国立防災科学技術センター(現・防災科学技術研究所)に納入し、埼玉県岩槻市の第1号観測井戸に使用され、その後全国の各地地震観測システムに納入されているほか、1976年(昭和51年)には気象庁に海底地震観測システムを納入、静岡県御前崎沖に敷設され、現在も観測が継続されています。
また、地熱発電所の設計や石油探査等の目的で深度2,000mにもおよぶ調査井戸にセンサーを懸垂し、計測データを伝送する地熱検層用ケーブルも開発され、各地で用いられるなど、特殊な計測分野でも大いに活躍しています。
北九州(現海底システム)事業所の完成と横浜2工場の閉鎖
海底光ケーブルの製造は横浜市の新山下工場と神奈川工場の2工場で行われてきましたが、2工場間が離れており、工場間の移動にケーブルを艀で運ぶという効率の悪さと、後工程である神奈川工場には1万トンクラスの敷設船が直接接岸できないことから、船積みには艀へ積み替えが必須であったため、1万トンの船が接岸し、一貫生産可能な工場建設が望まれていました。
そこで、日本全国北は北海道から南は鹿児島まで、工場立地の調査を行った結果、適切な港湾施設と、産業インフラの整備が優れた北九州市の響灘にこれに適した土地があることが判明しました。さらに北九州市の強い企業誘致の働きかけがあったことから、1994年(平成6年)2月に北九州市の響灘に建設を決断し、同年10月に着工し創業60周年に当たる1995年(平成7年)の8月末に工場が完成し、直ちに操業を開始しました。この北九州(現・海底システム)事業所はケーブルの製造能力が年間2万kmとなり、横浜に比べて約2倍の能力となりました。さらに1999年(平成11年)6月には将来の需要を見越して年産3万kmの能力に増強されました。
この新工場の完成に伴い横浜の設備は順次移設され、新山下工場は1996年(平成8年)1月に、神奈川工場は同年11月に作業を終了し、両工場の土地は売却されました。
なお、北九州(現・海底システム)事業所の開設を前にして、各工場への交通の便を考慮し、1966年(昭和41年)以来慣れ親しんだ渋谷区道玄坂から、JR浜松町駅に近い港区芝浦へ、1995年(平成7年)3月に本社を移しました。
商号変更
日本大洋海底電線という商号は1964年(昭和39年)の合併以来使われており、国内需要のお客様には「日海(にっかい)」、海外需要のお客様には「OCC」の略称でご愛顧いただいておりましたが、光ファイバを利用した新時代の通信インフラ構築に伴う新しい企業イメージ創出のため、1999年(平成11年)10月1日から従来略称として皆様よりなじみをいただいておりました「OCC(登記上はオーシーシー)」を商号と致しました。
本社移転、日本電気と住友電気工業のグループ企業化
2002年(平成14年)11月には大洋海底電線の創業の地である横浜市西区に本社を移転しました。また、2008年(平成20年)7月より日本電気株式会社と住友電気工業株式会社のグループ企業となりました。
現在のOCC
これまでの海底ケーブル製造実績は、40万㎞(地球10周分の距離)におよびます。海底という過酷な環境下で磨かれた品質・性能・信頼性の高い製品や技術力を、海底のみならず地球上の様々な環境で使われる製品群に展開しております。
海底通信分野においては、独自のユニークなケーブルデザインを踏襲することで品質・信頼性を維持しつつ、多心化、細径化といった高機能化と低価格化を狙った技術革新を続けています。一方で、生産能力増強を適宜実施しており、新たな顧客であるプラットフォーマーや、新時代への動きともいえるニューノーマル、デジタルトランスフォーメーションを意識した事業展開を進めております。
また、陸上線分野では、防水・防湿性、耐圧性等に優れた細径金属パイプ(M-PAC)光ケーブルについてこれまで国内市場でご好評をいただいておりましたが、ブータン王国(2013年(平成25年))を皮切りとしてネパール連邦民主共和国(2018年(平成30年))、モンゴル国(2019年(令和元年))、ツバル(2019年(令和元年))など海外のお客様への納入も果たすことができ、情報通信技術の向上へ貢献しております。
2025年(令和7年)で当社は創業から90周年を迎えることとなりましたが、創業以来培った経験や技術力を生かし、今後も引き続き世界的なコミュニケーション環境の構築をリードしてまいります。